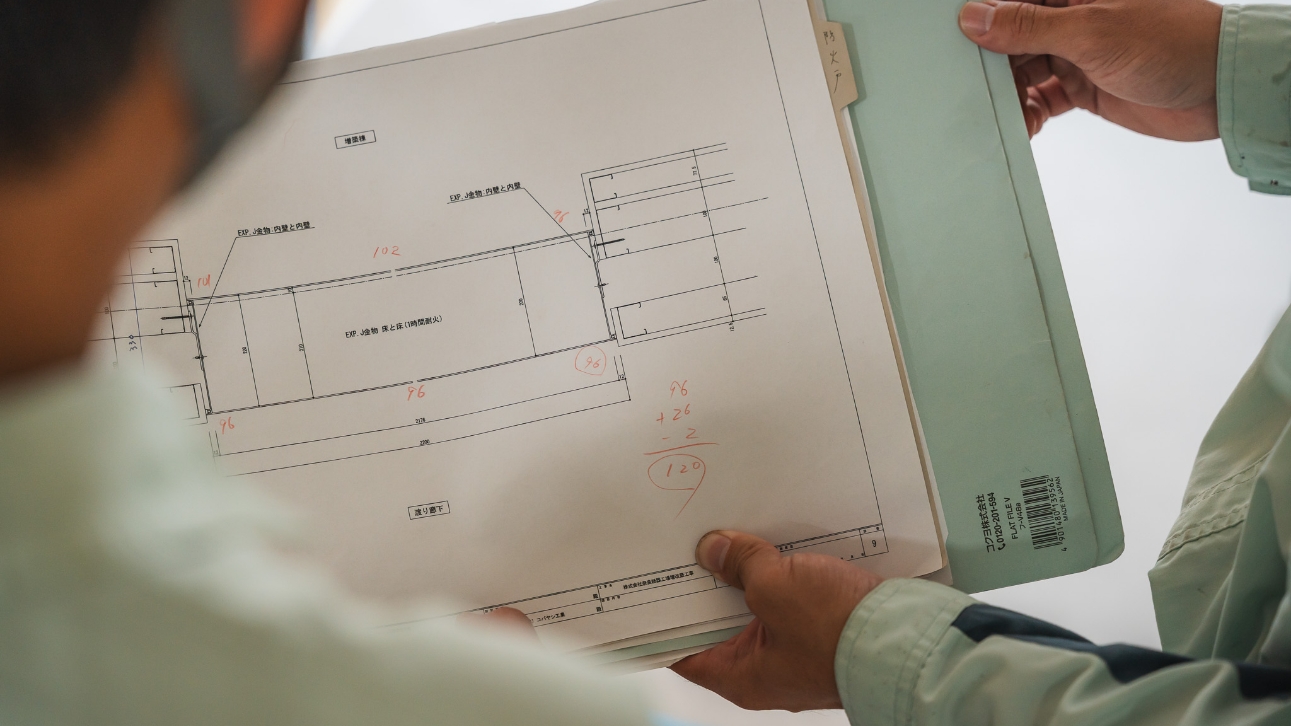富士山麓のような景勝地で、「暮らしの拠点となる家」や「週末を過ごすための別荘」の建築・リフォームを計画される方も多いかと存じます。どちらも大切な建物であることに変わりはありませんが、国の補助金や税制優遇を活用する上では、その建物が**「主として居住するための住宅」なのか、それとも「別荘」なのか**によって、扱いが大きく異なるという重要な注意点があります。
結論から申し上げますと、残念ながら、現在、国の主要な補助金や税制優遇は『ご自身が主に住むための住宅』を対象としており、『別荘』や『セカンドハウス』は対象外となるケースがほとんどです。
今回は、この重要な違いについて、その理由と具体的な制度の例を挙げて解説します。
なぜ「住宅」と「別荘」で扱いが違うのか?
国の住宅支援策は、国民の生活基盤である「住宅」の質の向上や、省エネ化の促進を主な目的としています。そのため、補助金の対象となるのは、原則として申請者が「常時居住する」または「主として居住の用に供する」家と定められています。
一方で、別荘やセカンドハウスは、生活に必須の住居というよりは、余暇や趣味のための資産と見なされるため、多くの支援策の対象から外れてしまうのです。
主要な補助金・優遇制度における「居住」の要件
具体的に、主要な制度でどのように定められているかを見てみましょう。
- 新築・リフォーム向け補助金(子育てエコホーム支援事業など) 現在実施されている大規模な補助金事業では、申請対象者は「住宅を所有し、居住する」ことが要件とされています。過去の類似事業である「戸建住宅ZEH化等支援事業」の要綱でも、「申請者が常時居住する住宅(別荘、セカンドハウス等は補助対象外)」と明確に記載されていました 。この方針は現在の制度でも引き継がれています。
- リフォーム向け補助金(先進的窓リノベ事業など) 窓や給湯器の高効率化を支援するリフォーム補助金も、基本的には所有者が居住する住宅が対象です。賃貸物件のオーナーが改修する場合は対象となりますが、オーナー自身が趣味や保養のために利用する別荘の改修は、原則として対象外となります。
- 税制優遇(住宅ローン減税など) 住宅ローン減税も、適用対象となる住宅の要件として「その者が主として居住の用に供する」家屋であることが定められています 。そのため、別荘の購入や建築のためにローンを組んでも、この減税制度は利用できません。
例外はある?別荘でも使える可能性のある制度
国の主要な制度の活用は難しい一方で、可能性がゼロというわけではありません。
- 地方自治体独自の補助金 移住・定住の促進や、観光地の活性化を目的として、自治体が独自に設けている補助金の中には、別荘や二拠点生活の拠点も対象となる場合があります。これらは「関係人口の創出」といった国の施策とは異なる目的を持つため、独自の要件を定めていることがあります。
- 補助金ではなく「融資(ローン)」 補助金(もらえるお金)ではなく、融資(借りるお金)の中には、セカンドハウスを対象とする商品もあります。例えば、住宅金融支援機構の「リ・バース60」や「グリーンリフォームローン」では、セカンドハウスの取得やリフォームも融資の対象としています 。
計画の第一歩は、用途の明確化から
このように、補助金を活用した賢い資金計画を立てるためには、家づくりの初期段階で、その建物の法的な位置づけを明確にすることが不可欠です。
私たちコバヤシ工業では、お客様の建築計画をお伺いする最初の段階で、その建物が「住宅」と「別荘」のどちらに該当するのか、そして、それによってどの優遇制度が活用できる可能性があるのかを丁寧に整理し、ご説明します。特に、将来的に移住も考えているといったケースでは、住民票の扱いなども含めて慎重な検討が必要です。
補助金の活用は、家づくりの総費用を左右する重要な要素です。計画の初期段階から、ぜひ専門家である私たちにご相談ください。