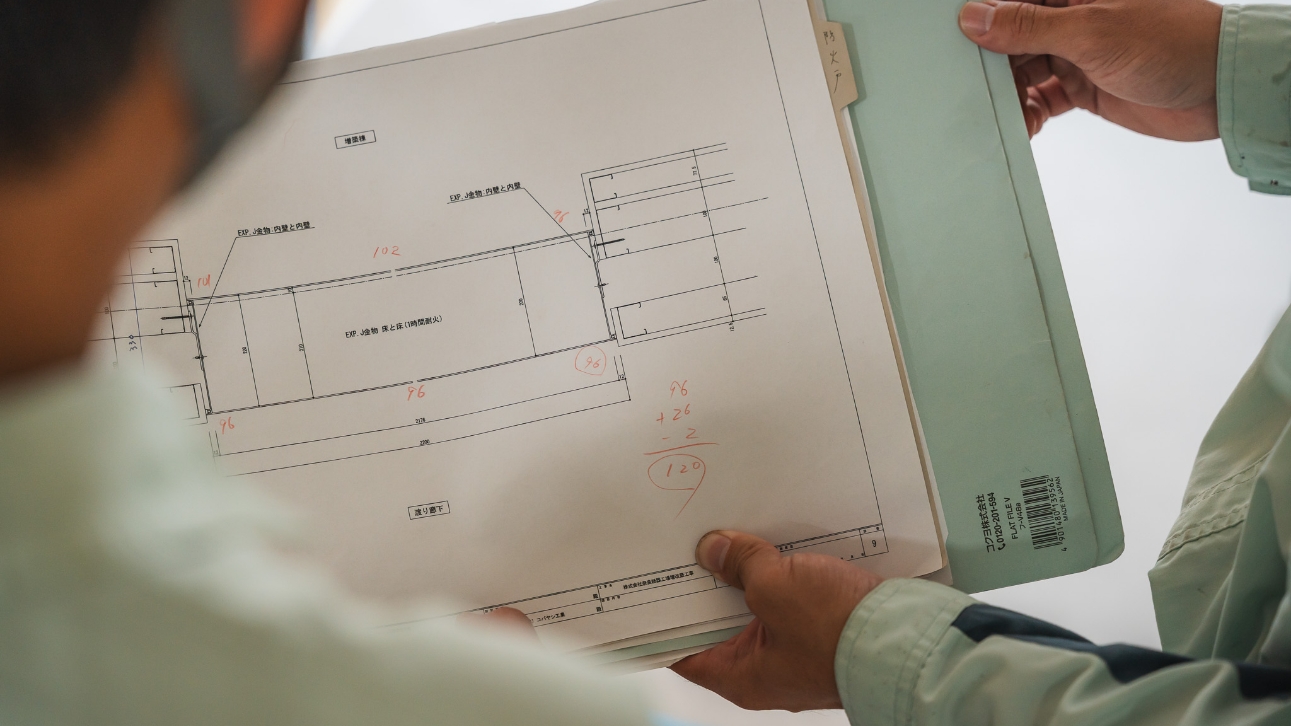導入:夢を語る前に、コバヤシ工業と描く設計図
マイホーム。それは人生最大のプロジェクトです。「いつかは欲しい」という夢を、私たちはコバヤシ工業として「確かなカタチ」に変える使命を担っています。しかし、どんなに素晴らしい木造建築も、土台となる「構造計算」が間違っていれば、着工はできません。
マイホーム計画における構造計算こそ、お金の計画、すなわちファイナンシャルプランニング(FP)です。
設計・現場監督の経験も持つ当社だからこそ、単なる住宅のプロとしてではなく、お客様の人生全体を見据えるFPの視点を融合させます。感情論ではなく、データとロジックに基づき、お客様の未来を支える**「強固な資金の土台」**を築くための思考のフレームワークを提供します。
本コラムでは、全5回にわたり、「夢」を「実現」へと変えるロードマップを、コバヤシ工業のプロフェッショナルな視点と共にご提示します。
第1回:資金計画のゴール設定 – 「住宅価格」ではなく「総額」を見よ
住宅計画で最も危険な誤解は、「建物本体価格」や「土地代」だけを見て予算を組んでしまうことです。コバヤシ工業が提供する住宅のプロとしての品質を維持し、お客様に安心して暮らしていただくためには、必ず**「総事業費」**で計画を立てる必要があります。
1. 見積もるべき「3つの総額」
計画の土台となる「総事業費」は、以下の「3つの総額」で構成されます。特にBの「諸費用」こそ、資金ショートを防ぐ鍵となります。
| 費用区分 | 主な内容(建築のプロとして見落とさない視点) |
| A. 住宅本体・土地費用 | 土地代、建物本体工事費、付帯工事費(コバヤシ工業の外構設計、地盤改良、ライフライン引き込みなど) |
| B. 諸費用(購入時) | 不動産取得税・登録免許税・印紙税などの法律に関わる税金、融資手数料、火災・地震保険料(長期一括払いの検討)、建築確認申請費用・設計監理費用など。 |
| C. 予備費・引越し費用 | 新しい家具・家電、引越し代、仮住まい費用、予備費(計画外の出費への備え)など |
【計画の構造式】
マイホーム総事業費 = A + B + C
当社の営業担当者は、木造住宅の現場経験や、建築基準法に関わる申請業務の知見も活かし、特にBの諸費用や付帯工事費について、お客様に見積もりの段階からクリアに提示し、資金計画の精度を格段に高めます。
2. 資金調達の「バランス構造」を考える
この確定した総事業費をどのように賄うか、「自己資金(頭金)」と「住宅ローン(借入金)」の最適なバランス構造を決定します。
自己資金(頭金):
**「総事業費の20%」**を目安とすることで、ローンの借入額を抑え、将来の利息負担を軽減できます。ただし、注意すべきは、手元の資金を全て住宅に投じないことです。
【FPからの警鐘】「生活防衛資金」は聖域です
住宅取得後も、緊急の出費(病気、突然の失業、家電の故障など)に備えるため、生活費の最低6ヶ月分〜1年分は必ず手元に残してください。この「生活防衛資金」を確保した上で、残りを頭金に充てるのが鉄則です。
住宅ローン(借入金):
自己資金で賄えない残りの部分です。ここで最も重要な視点は、**「銀行が貸してくれる額」ではなく、「お客様が無理なく返せる額」**を見極めることです。
まとめ:コバヤシ工業とともに「逆算」で始める
マイホーム計画は、まず「総事業費(ゴール)」という設計図を正確に描き、そこから自己資金と借入金の「バランス構造」を決定するという逆算のプロセスで始まります。
この強固な土台が、お客様の人生全体を支えるコバヤシ工業の家づくりを可能にします。次回は、この「総額」をもとに、あなたの人生設計に合った「無理のない借入可能額」を算出する、具体的な家計の耐久性チェックに入ります。